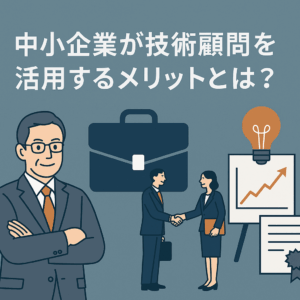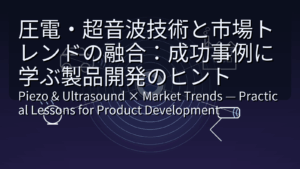形式と実質の乖離 ― 技術者から見た日本社会の“建前主義”
NHKの人気番組『魔改造の夜』は、技術者が既存の製品を大胆に改造し、ユニークな競技に挑む姿を描く。
技術の面白さを広く伝えるという意味で、この番組は成功しているだろう。
しかし、私はどうしても映像の中のある光景や番組全体に違和感を覚える。
番組は企業名を“伏せている”はずなのに、作業服や背景には堂々と社名やロゴが映っている。
また、本業でどんどん国際競争力が低下していることにも関わらず、あたかも世界一のような演出である。
これは単なる番組演出の問題ではない。
むしろ日本社会全体に広がる「形式と実質の乖離」の一断面である。
建前と本音の共存
私たちの国では、「建前」と「本音」が長く共存してきた。
建前は体裁を整え、関係者の面子を守る。
本音はその裏で現実を動かす。
憲法と自衛隊の関係は、その象徴的な例だ。
憲法九条は戦力の保持を禁じるが、現実には高度な装備と組織を持つ自衛隊が存在し、
その運用は「解釈」によって正当化されている。
職場でも同じだ。
働き方改革で残業時間を減らす建前の一方、持ち帰り仕事やサービス残業は温存される。
制度の条文や方針は変えず、運用で現実に合わせる。
こうした曖昧な調整は「柔軟性」として評価されることもあるが、
科学技術の現場から見ると、これは単なるロジックの破綻である。
技術者の視点からの苛立ち
自然科学や工学の世界では、因果関係は明確で、前提条件が変われば結果も変わる。
曖昧な前提や都合の良い解釈を積み重ねれば、実験は再現できず、設計は破綻する。
技術者が形式と実質の矛盾を放置することは、致命的な事故や製品不良を招く行為に等しい。
それだけに、この社会的な「いい加減さ」には苛立だしさも覚える。
『魔改造の夜』の企業名ぼかしは、もしかすると些細な例に見えるかもしれない。
しかし、そこには「体裁を守れば実質は問われない」という文化の縮図がある。
そしてこの感覚が、より深刻な政策や制度運用にも影を落としているのだ。
信頼を築くために
私たちが科学技術の信頼性を守り、国際競争力を保つためには、
建前と本音を一致させる習慣を社会全体で育てる必要がある。
制度を変えるべきなら変え、ルールは守るべき時に守る。
それは面倒で、衝突を生むかもしれない。
しかし、自然科学の世界、ひいてはグローバル化した社会では、それこそが信頼の基礎であり、
未来を築くための唯一の道である。